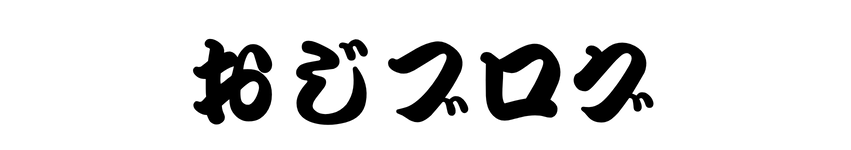PRを含みます。
着物を普段から着用していたり、着付けに興味があったりする方は、「成人式に自分で着付けをしてみたい」と考えることもあるでしょう。
また、自分で着付けができたら、費用面も抑えられる点もメリットです。
振袖は着物に比べて袖が長いだけでなく、帯のバリエーションもさまざまなので、着物と比べると自分で着付けることが難しい部分もあります。
正しい知識と技術を身に付けることで、自分で振袖を着付けることも可能となるでしょう。
そこでこの記事では、振袖を自分で着付ける方法を紹介します。
着付けの手順をマスターするだけでなく、着付けに必要なアイテムも確認しておきましょう。
自分で着付けをして迎える成人式はより思い出深くもなります。
興味のある方は、ぜひチャレンジしてみてください。
振袖を自分で着付けるのは難しい?
振袖を自分で着付けるのは難しいものです。
特に、普段から着物になじみのない方の場合、どのようなアイテムをどのように使用するかなど分からないことが多いでしょう。
また、振袖は通常の着物と比べて袖が長いこともあり重さもあるため、ひとりで着付けをすることが非常に困難ともいわれています。
しかし、周囲のサポートを受けたり、帯結びの方法を考慮したりすることで、キレイに着付けられることもあるでしょう。
まずは、自分で振袖の着付けをすることの難易度を確認していきましょう。
振袖の着付けには専門的な知識が必要
着物を着付ける際は、着付けの知識と技術が必要です。
特に振袖は、着物よりも着付けが難しいといわれています。
着付け教室の中でも、振袖は難易度の高いレッスンとして設定されていることもあるでしょう。
また、振袖に合わせる帯の結び方には多彩な種類があるため、結び方によっては自分ひとりで帯を結べないかもしれません。
華やかな帯結びで美しい着こなしを実現したいのであれば、着付けのプロにお任せしたほうが無難かもしれません。
しかし、着付けの知識や技術を少しでも身に付けておくと、成人式当日、振袖が着崩れてしまったときに対応できます。
もしものときにお直しできるよう、勉強しておくのもおすすめです。
振袖の着付けが難しい理由
振袖の着付けが難しい理由として、帯結びのバリエーションの多さが挙げられます。
一般的な結び方をアレンジした、「変わり結び」を用いることが多い点も振袖の特徴です。
振袖の雰囲気に合った変わり結びを学んでおくことは、よりおしゃれで華やかな振袖姿を完成させるためには必須です。
また、振袖は通常の着物と比べて袖の長い点が特徴です。
そのため重さもあります。長く、重い生地の振袖を自分ひとりで着付けることは難しいともいわれています。
なお、帯結びの中には自分ひとりで結べるものもありますが、結び方にこだわりたい場合は、経験が豊富な方に帯結びをお願いするほうが安心できるでしょう。
帯結びを用意しておけば自分で着付けることは可能?
自分ひとりで振袖の着付けをしたい場合には、先に帯結びを用意しておく方法もあります。
振袖を着た後に、自分で帯を結ぶのは難しいものです。
しかし、帯結びを作っておくと、楽に帯を巻けるようになります。
先に帯を作っておく場合、改良枕を活用するとよいでしょう。改良枕とは、帯結びを手早くするための帯枕で、多くの着付け教室でも利用されているアイテムです。
振袖を自分で着付ける際に用意するアイテム
振袖を着付けるときには、まず、着付けに必要なアイテムを用意しなければなりません。
ここでは、振袖を着付けるときの必須アイテムについて見ていきましょう。
また、自分で着付けをする際に便利なアイテムや、振袖を美しく着こなす補正アイテムもピックアップしました。
まずは、これらのアイテムを準備し、使い方についても確認しましょう。
振袖の着付けに必要なもの
振袖を着付けるときには、以下のアイテムが必要です。
| 必要な着物類 | ・振袖 ・帯 ・帯締め ・帯揚げ ・伊達衿(だてえり) |
| 必要な肌着類 | ・肌襦袢(はだじゅばん) ・裾よけ ・足袋 ・タオル ・補正パッド ・長襦袢(ながじゅばん) ・半衿(はんえり) ・衿芯(えりしん) |
| 必要な小物 | ・腰ひも ・伊達締め(だてじめ) ・前板 ・後板 ・帯枕 ・三重仮ひも |
なお、上記のアイテムに加えて、振袖姿を彩る「髪飾り」「バッグ」「草履」も必要です。
振袖の雰囲気に合ったものを選びましょう。
あると便利なアイテム
振袖を着付けるときに、あると便利なアイテムは以下の通りです。
準備することで、大変な着付けも多少は楽になるでしょう。
〈コーリンベルト〉
ゴムひもにクリップが付いているアイテムです。
着物ベルトや着付けベルトとも呼ばれることも。衿が崩れるのを防いでくれる役割があります。
〈ウエストベルト〉
腰ひもと同様の役割があります。
振袖の着崩れを防いでくれるため、長時間振袖を着るときに重宝するアイテムです。
〈マジックベルト〉
長襦袢の上から締めるマジックテープのベルトです。
衿元の着崩れを防いでくれる役割があります。
補正アイテムも忘れずに
着物を着付ける際には、補正アイテムを使います。
補正アイテムは、着物姿を美しいものにするために必要なアイテムで、振袖を着付けるときにも必要です。
着物は洋服と異なり、身体のラインが出ない作りになっています。
そのため、補正をせずに着物を着付けるとシワができて美しく着こなせないこともあります。
そこで必要となるのが、身体のラインを目立たなくするための補正アイテムです。
補正アイテムでは、ウエストやヒップの上、バスト部分を補正するケースが多いでしょう。
なお、補正アイテムにはタオルを利用することも多いですが、ウエストパットやバストパットなどの専用アイテムも存在します。
振袖を自分で着付ける際の手順
ここからは、振袖を自分で着付けるときの手順を見ていきましょう。
着物には正しい着付けの手順があるため、手順に沿って振袖を着付けましょう。
また、しっかりと事前準備をしておくことも、着付けの負担を軽減させるポイントです。
前日までにしておきたい準備も確認して、できるだけスムーズに着付けができるようにしましょう。
1.和装下着を着用する
はじめに、和装用の下着を着けます。振袖を含め、着物は寸胴であるほど美しい着こなしができます。
洋装用のブラジャーは、胸を強調させてしまい寸胴に見せるのが難しくなってしまう場合があるため、和装用のブラジャーを用意しておくとよいでしょう。
次に、肌襦袢や裾よけといった肌着類を身に着けましょう。
これらのアイテムには着崩れを防ぐ効果があります。
また、裾よけは、振袖を着付けた後に歩きやすくなる役割もあるものです。
なお、下着や肌着を用意する際は、吸収性のよいものを選びましょう。
肌着が汗を吸収してくれると、上に身に着けると長襦袢が汚れません。
2.足袋を履く

和装下着を身に着けたら、はじめに足袋を履きましょう。
振袖を着付けたあとに足袋を履くと、足袋を履くときの着崩れが心配です。
振袖に限らず、着物を着付けるときには、足袋は肌着を身に着けるときに履いておくのが基本の流れということを覚えておきましょう。
3.補正をする
次に、補正アイテムを使って補正をしていきます。
ウエストパットやヒップパットを使うとスタイルに合わせて補正しやすいでしょう。
ウエストパットやヒップパットがない場合には、薄手のタオルでもOKです。
スタイルに合わせて凹凸のないように補正すると、着崩れを防げたり、着物にシワが寄らなくなったりなど、美しい振袖姿を実現できます。
また、腰やお尻の部分をしっかりと補正すると、キレイに帯が結べるでしょう。
4.長襦袢を着用する
下着と肌着を身に着け、補正をした後は、長襦袢を身に着けます。
長襦袢は汗から振袖を守ってくれるアイテムです。
長襦袢にはさまざまな種類がありますが、振袖の下に身に着ける長襦袢は格のある礼装用のものを選びます。
長襦袢には衿芯を通しておきましょう。
袖を通したらしっかりと中心を合わせると、着崩れを防げ、美しい着こなしができます。
次に、こぶしひとつ程度の衣紋を抜きましょう。
衣紋とは、振袖の後ろの衿部分を指します。
衣紋を抜くことは、襟の後ろを少し引き下げることをいいます。
衣紋を抜いたら、衿合わせをします。
ここで、しっかりと衿の角度を調整しておきましょう。
下前と上前を合わせたら、合わせひもを締めます。
合わせひもを締めたら、背中のシワや脇のたるみをとり、伊達締めを締めましょう。
5.振袖を着用する
振袖を着るときは、まずは袖を通します。
袖を通したら、振袖の衿を持ってキレイに羽織り直しましょう。
しっかりと背中心を合わせるのがポイントです。
次に、裾合わせをします。
裾は、くるぶしが隠れる程度が理想の長さです。
下前の位置を決めたら、上前も腰元に合わせて腰ひもでしっかりと固定します。
腰ひもは緩いと着崩れの原因になり、締めすぎると苦しくなるため、加減を調節するのがポイントです。
次に、裾の長さが変わらないよう注意しながら、身八つ口から手を入れておはしょりを整えます。
整えたら、コーリンベルトをとめて伊達締めで固定しましょう。
おはしょりは振袖姿を美しく見せるために大切な部分なので、ラインを意識して丁寧に作ります。
6.結帯を結ぶ
振袖には、さまざまな結び方を用います。
結び方によってはひとりで結べない場合もあるため、まずはどの結び方にするかを決めておきましょう。
ここでは、振袖によく用いられる「立て矢結び」を例に紹介します。
1.手先の長さを決める
2.はじまりを左脇に合わせてふた巻きする
3.たれ先を斜めに折り上げる
4.手先を3つ折りにする
5.帯の上線でひと結びする(手先は上)
6.羽根の大きさを決める
7.たれを内側へ折り込む
8.帯枕を羽根の間へ入れる
9.羽根を整えてひもで固定する
10.帯締めを結ぶ
11.羽根の形を整える
以上の手順で、華やかな立て矢結びができます。
スムーズな着付けには事前準備が必須

自分で振袖を着付けるときには、入念な事前準備が欠かせません。
成人式の当日に準備をするとなると、スムーズな着付けは難しくなります。
必要なものは当日までに揃えておくことが大切です。
着付けの経験が豊富な方も、前日までには以下の準備を終えていることがほとんどでしょう。
・着物や帯をハンガーに掛ける
・半衿を長襦袢に縫い付ける
・足袋と帯揚げにアイロンをかける
・小物を準備しておく
着物や帯をタンスなどにしまっている方は、前日までに出しておくと当日に慌ててシワを取ることを防げます。
また、長襦袢に半衿を縫い付ける作業も時間がかかるため、事前にしておきたい準備です。
また、小物は使う順に並べておくと、スムーズに着付けができます。
振袖を自分で着付けるときの注意点
慣れない振袖姿で成人式を過ごすと、振袖が着崩れしたり、苦しくなってしまったりすることもあります。
そのため、自分で振袖を着付ける際には、着崩れや気心地についても気を配る必要があります。
ここからは、振袖を着付ける際の注意点だけでなく、着崩れをした際の対処法について見ていきましょう。
着崩れをしやすい
成人式当日は、振袖を着付けることから始まり、式典や同窓会、祖父母や親戚などへあいさつするなど、かなり長い1日になることが予想されます。
移動の途中で振袖が着崩れしてしまったり、座っているときにたるみができてしまったりということもあるでしょう。
たるみが気になってしまうときは、おはしょりの中側からおはしょりを上に引くと、シワやたるみがキレイになります。
着付けをプロにお願いする場合でも、着崩れしたときの対処方法を知っておくと、美しい着物姿で成人式の1日を過ごせるでしょう。
締め付けにより苦しくなりやすい
自分で着付けをすると、腰ひもを結ぶ加減がうまく調節できずに、苦しくなってしまうことがあります。苦しくならないように着付けるためには、幅の広い腰ひもを使用するのがポイントです。
また、補正の際にタオルを使用することで、おなかなどにひもが食い込むことを避けらるでしょう。
また、腰ひも、胸ひも、それぞれの結び目をずらすのもポイントです。
着付けには複数のひもを使うため、全てのひもをしっかり締めると苦しくなりやすいでしょう。
着崩れしにくい部分のひもは締め付け加減を緩めにするなどの調整をすると、振袖着用時の気心地も変わってきます。
振袖を自分で着付けるための勉強方法
着物の中でも、着付けが難しいとされるのが振袖です。
振袖を自分で着付けるとなれば、着付けに慣れているプロでも大変だと感じることも多いようです。
しかし、事前にしっかりと着付けの勉強をして、当日の流れを頭でシミュレーションしておくと、自分ひとりでも振袖の着付けが可能でしょう。
また、成人式で振袖が着崩しれたときに役立ちます。
この機会に振袖の着付けについて勉強をしたいと思った方は、これから紹介する勉強方法でぜひ挑戦してみてください。
無料動画や着付けレッスンを活用しよう
最近では、無料動画を使っても着付けが学べます。
着付けのプロが、着付けについて分かりやすく解説している動画もたくさんあるため、動画で勉強するのもひとつの方法です。
着付けを丁寧に学びたい方は、着付けのスクールに通うのもよい方法です。
初心者向けの着付けのスクールを選ぶと、基礎的な部分を含め、着付けについてしっかりと勉強できるでしょう。
また、動画ではイマイチつかみにくい帯の結び方のテクニックなども学べます。
成人式当日はヘアセットやメイクの準備も必要

成人式当日に自分で着付けをする方は、ヘアセットやメイクの準備についても考える必要があります。
振袖に似合うゴージャスで華やかなヘアセットやメイクをしたい場合は、美容室などにお願いする必要があります。
美容室などは予約が必要なので、着付けの予約が必要ではないからといって、忘れてしまわないよう注意しましょう。
また、着物をレンタルする店舗で着付けとヘアセット、メイクがお願いできることもあります。
成人式の記念写真を撮影する場合には、着付けやヘアセットがセットになっているスタジオを利用するのもおすすめです。
まとめ
着物の着付けは簡単にできるものではありません。
特に振袖は着付けるのが難しい着物なので、着付けるためには知識と技術が必要です。
成人式当日に振袖をご自身で着付けるのは難易度が非常に高いですが、事前に着付けについて学んでおくなどして挑戦してみるのもおすすめです。